成年後見制度
成年後見制度とは

- 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な人たち(以下「本人」という。)は、財産管理や介護保険を利用するといった契約を自分で行うことは困難です。また、悪質な商法の被害にあうおそれもあります。
- 成年後見制度は、契約を本人に代わって行ったり【代理権】、本人が誤った判断で契約をした場合は、その契約を取り消すことができる【同意権・取消権】などの権限を、家庭裁判所が選任した成年後見人等に与え、本人の生活状況に応じた保護や支援を行う制度です。
種類
- ■任意後見制度(判断能力が不十分になる前)
- 将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
- ■法定後見制度(判断能力が不十分になった後)
- 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
- ◎法定後見制度の3種類
-
後 見 補 佐 補 助 対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 申立てが出来る方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長等 成年後見人等の権限 必ず与えられる権限 財産管理についての全般的な代理権、取消権
(日常生活に関する行為を除く)特定の事項※1についての同意権※2、取消権
(日常生活に関する行為を除く)― 申立てにより与えられる権限 ― 特定の事項※1以外の事項について同意権※2、取消権
(日常生活に関する行為を除く)
特定の法律行為※3についての代理権特定の事項※1の一部についての同意権※2、取消権
(日常生活に関する行為を除く)
特定の法律行為※3についての代理権制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど ― -
※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。
ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。 - ※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
- ※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
- 民法13条1項に定める行為は、全部で9つになります。
- 貸金の元本の返済を受けること。
- 金銭を借り入れたり、保証人になること。
- 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
- 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
- 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- 新築・改築・増築や大修繕をすること。
- 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
手続き・申請方法
- ■手続きの流れ
-
-
申立
原則、本人が居住する地域の家庭裁判所に申し立てます。
後見制度の費用は・・・
申立て時:収入印紙(800円)、登記印刷(4,000円)、郵便切手、診断書(金額は医療機関による)、鑑定費用10万円程度が必要です。 -
審判手続
(1)調査 : 調査官が事情を調査
(2)鑑定 : 医師が本人の判断能力を鑑定
(3)審問 : 必要に応じて調査官が直接事情聴取 -
審判
(1)裁判官による審判
(2)家庭裁判所から審判書送付 -
援助開始
後見人は、配偶者、親族に限らず、司法書士、弁護士、社会福祉士などの第三者が選任されます。(法人も可)
-
申立
- ■裁判所が刊行しているパンフレット
- ☆成年後見制度-詳しく知っていただくために-
- ☆成年後見制度を利用される方のために
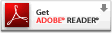 ファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
ファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
右記ボタンをクリックし、アドビ システムズ社のサイトからダウンロードを行い、インストールしてください。